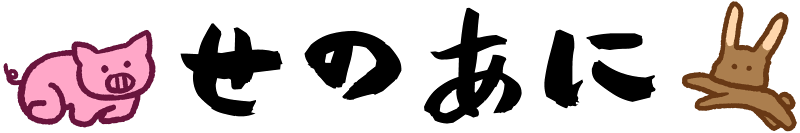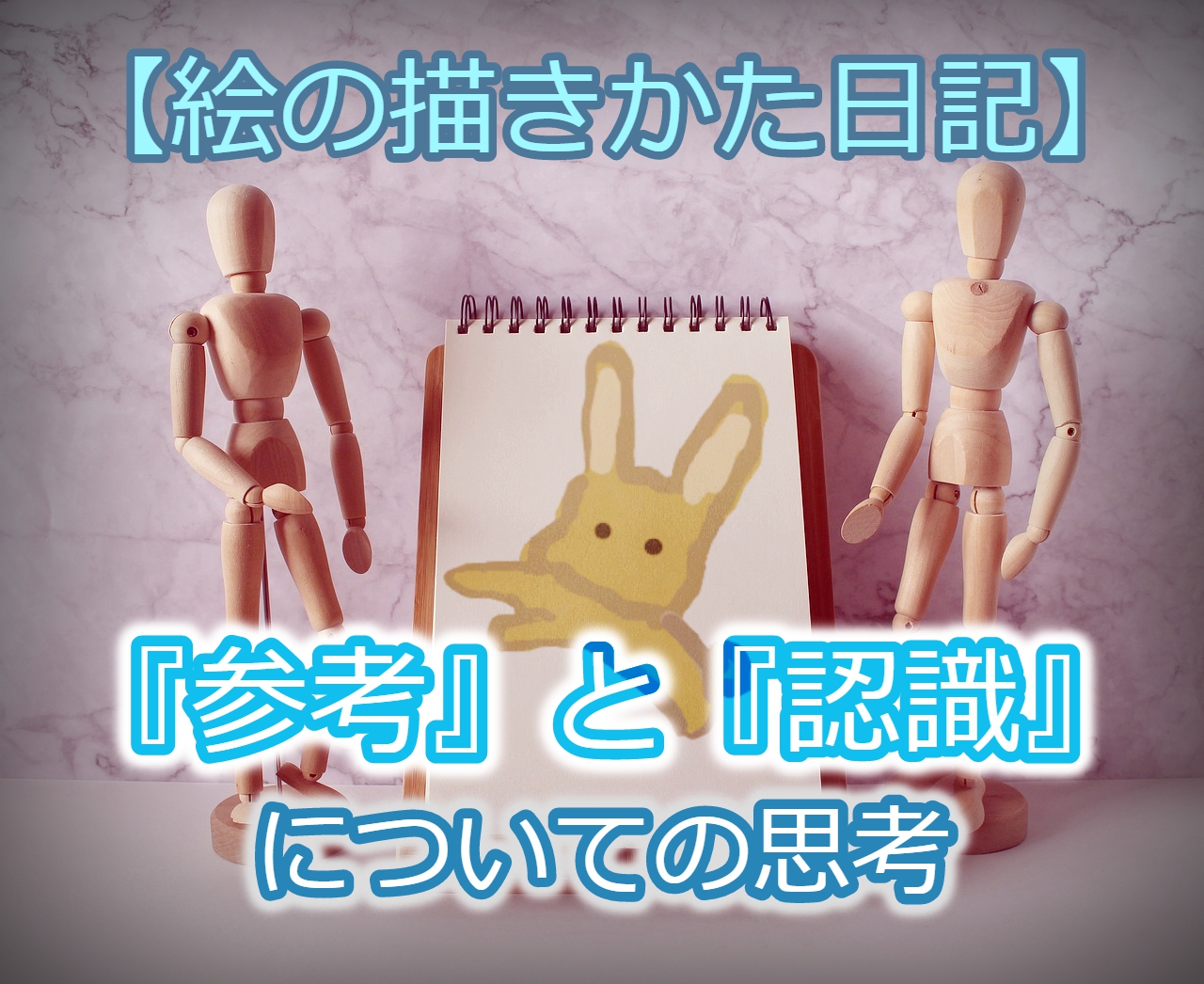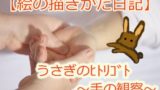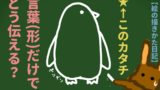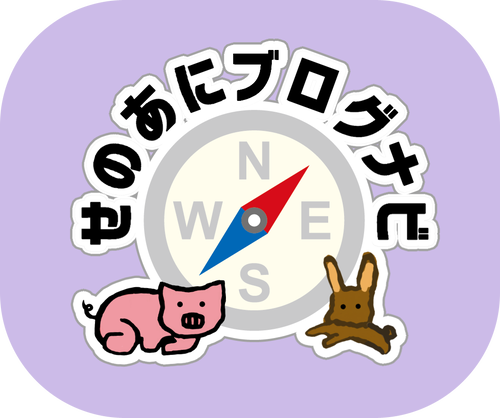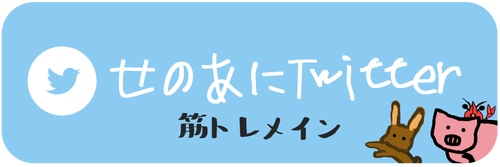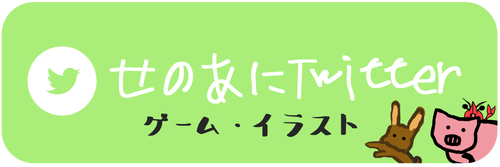こんにちは。せのあにこと世界のアニマル、うさぎのぴょいんです!
先日書いたお絵描きの日記で、『認識をすることが大事』というお話をしました。
今回はちょこっとそのお話の続きで、『参考にすること』について思ったあれこれを書いていきたいと思います。
参考にするということ
前回の絵の描きかた日記の中で、手を描く例を挙げて
『増えていく情報』と一緒に『形になっていく手』を描いてお話をしましたが、
『認識』を増やしていこうという時に大変役立つのが、参考書だと思っています。
ひとつの『モノの見方』
ぴょいんはあたまでっかちなところがあるので、
昔は『絵の参考書とか参考にしたら負け』みたいに思っていました←
脳トレをしすぎて頭がわれてしまったぴょいん
ケツアゴならぬケツアタマです。 pic.twitter.com/BYFFCYGbDJ
— 世界のアニマル (@sekainoanimaru) November 17, 2019
あたまでっかちなぴょいん。
参考書とはいえ、それが世の中の絶対的なルールとかじゃないから信用しきってしまうのも怖いし。
『頭身はこんな間隔ですよ、目鼻はこんなバランスで・・・』などと比率とかをいきなり提示されても、
「人の体のサイズなんて人それぞれなんだから、参考書の通りに覚えてしまってはいけない気がする。」
などとゴタクを並べて、素直に受け入れられませんでした。
あたかも『これが基礎』みたいに言われると、押し付けられているようで、自由が無くなりそうな気がして反発していたんでしょうか・・・(それでもちょっと参考にしたりしてたけど←
そんな風に思っていたのですが、最近になって少し考え方が変わってきました。
『たくさん認識することで描けるようになっていく』という考え方から言うと、
参考書というものは、要は『ひとつのモノの見方』が示してあるだけなんだなぁ・・・と思ったんです。
ただの、どこかの誰かの1つの意見なんだなと。
認識に沿っていない
どうして参考書は抵抗があるんだろう(ぴょいんだけかもしれませんが)と考えてみると、
説明の仕方が、『認識』に沿っていないからなんじゃないかと思います。
よく見る頭身の図解とか、手の参考図がバーッと並んでる参考書とか・・・
実際の絵にすることで、明確に構造を分かりやすく表しているのかもしれないけれど、
「ここはこう描くといいですよ。」と、過程(認識)の無い答えだけ示しているんです。
それは、言ってしまえば『現物の手を見ているのと同じ』だと思います。
それを見て覚えられれば、最初から自分の手でも参考にして、スッと描けるようになっているハズなんです。
情報量が多すぎるから覚えられない
もう少し掘り下げて考えてみると・・・
どうして、現物を見て覚えられない(描けるようにならない)のか?といいますと・・・。
『情報量が多すぎるから』ではないでしょうか。
試しに、自分の手を見ながら、5本の指を曲げてみてください。
その時同時に起こっている変化は、どれぐらいあるんでしょう?
こんなの1度に認識するの、難しすぎませんか・・・ぴょいんは完全に処理落ち←
こんなに情報がたくさん入ってきては、脳が混乱して把握も追いつきません。
簡略化して認識するとよし
なので最初は、ある程度簡略化して認識する必要があります。
その一例が、『全身の長さを頭何個分かではかる』であったり、『部位ごとに切り離して形を覚える』だったりします。
「頭身」という言葉が浸透しているから、なんでもかんでも頭が何個分かで表さなきゃならない気がしちゃいますが、
本当はそんなこともなく、腕の長さで測ったっていいし、太ももの長さで表したっていいわけなんですよね。
つまり自分の好きな計り方でモノの長さや大きさを表していいんです。
(当たり前のことを言ってるだけかもしれないけれど、ぴょいんにとっては忘れがちなことなので;==)
そうして、全身の比率などを簡略に示した基準を頭に入れて、
その基準を元に、今度は自分でアレンジした比率を用いたオリジナルの絵が描けるようになっていけばいいんです。
自分で1から現物を観察して『認識』をしようとすると、気が遠くなりそうなその作業を
ある程度見やすく、覚えやすく示してくれているのが『参考書』。
どこかの誰かの1つの意見ではあるけれど、その人が発見してくれたその測り方が覚えやすいものであれば、大変参考になるものなんだなぁと思いました。
まずは自分で発見してみる
参考書は大変タメになる、という考え方をあげてみましたが、「参考書をそのまま鵜呑みにすればOK!」ということでもなく。
より効果があると思うのは、『まずは自分でできる限りの発見をしてみて、次に他の人の発見を見てみる』というやり方です。
どんどん理解が深くなりますし、
まずは何よりも、『納得』ができなければ身にならないと思うんです。
納得をするために、まずは軽くでもいいので自分で研究してみて、自分の発見を前提に置いてから他の人の発見を組み込んでいってみる。そうすると認識もしやすくなると思います。
絵が固くなる?
たくさんを見て、たくさんを知ることで、その存在が必ず絵にいきてくると思っています。
しかし一方で、もしかしたら「知識が深まれば深まるほど、絵が固くなってしまう?」という不安も出てきたり・・・
体の線はこうだから、これ以上長い線はあり得ない!とか
この物の仕組みはこうだから、絶対この形以外にならない!とか。
けれどそれも、「知れば知るほどアレンジの幅が広がる」と思ったらいいんです。
「だって現実ではこうならないし・・・」と思ってしまうようなことを、
表現できて可能に変えられるのが、創作の良いところですからね・・・(*´= =`)
目的は画力の習得なのか、発見を楽しみたいのか
誰かが既に見つけた発見を、自分も1から同じ発見をしようとしても、難しいし時間もかかります。
自分で仕組みを解明すること自体が楽しくて仕方がない人なら、それを楽しむ目的で取り掛かれば良いと思いますが(夏休みの自由研究で昆虫標本を作るのとか)、
『体が描けるようになりたい!』などの『画力の習得』が目的であれば、参考書や他の人の意見をどんどん取り入れていくべきではないかと思います。
何もかも1から、全て自分の発見で上達していく!ということは、
大げさな例えかもしれませんが『画家になりたいから、まずは絵の具と紙を作ることから始める!』と言っているのと同じ感じなのかもしれません((
ぶーぶーが筋トレをしたいからって、プロテインの発明から取り掛かってるとか・・・?(笑
既にあるツールを存分に駆使して、自分の高みを目指して成長していけたら良いんじゃないかと思うのです。
参考=認識フィーバー!
世界中でたくさんの人が、様々な見方でものの描き方を考えていて、
今の時代は、そのたくさんの発見が本やネットから簡単に享受できる夢のような時代だと思います。
まとめになりますが、大切だと思うのは
ということです。
そうすることで、どんどんと自分が心から描きたい絵が描けるようになっていけると思います。
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
自分への戒めも兼ねて、個人的に大切だと思っていることを書かせていただきました。
自分でももっと実践できるように、見返しながら精進していけたらと思います。

読んでいただき、ありがとうございました!